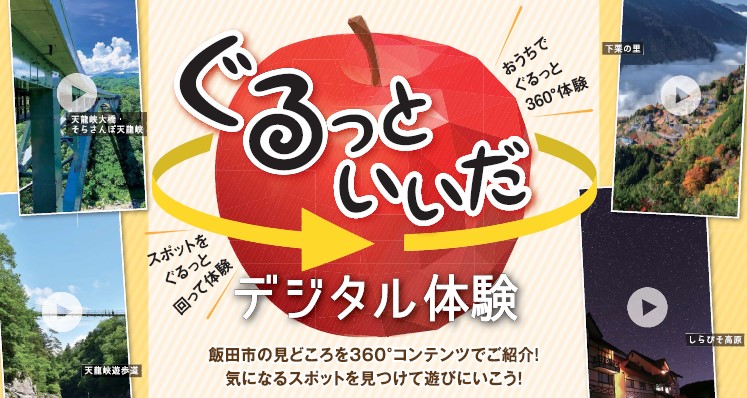タグ:郷土料理
「塩イカ」は、イカの内臓を取って皮をむき、茹でて塩漬けにした塩蔵食品です。 江戸時代中期ころから海沿いのまちで作られ、「塩の道」を通り、塩そのものと一緒に内陸へ運ばれてきたと伝えられています。 冷蔵や冷凍の技術がなかった昔、海なし県の長野では海産物がとても貴重な食べ物でした。 保存性が高く、味も良い塩イカは長野県中部地域、南部地域を中心に定着しました。地元のスーパーで販売しています。【食べ方】塩抜きをしてキュウリとあえた粕もみ。
「塩イカ」は、イカの内臓を取って皮をむき、茹でて塩漬けにした塩蔵食品です。 江戸時代中期ころから海沿いのまちで作られ、「塩の道」を通り、塩そのものと一緒に内陸へ運ばれてきたと伝えられています。 冷蔵や冷凍の技術がなかった昔、海なし県の長野では海産物がとても貴重な食べ物でした。 保存性が高く、味も良い塩イカは長野県中部地域、南部地域を中心に定着しました。地元のスーパーで販売しています。【食べ方】塩抜きをしてキュウリとあえた粕もみ。
馬刺しだけではない、バラエティに富んだ美味しい馬肉料理【馬肉とは?】“桜肉”と呼ばれる馬の肉。南信州地域では古くから馬を様々な調理法で食べる習慣がありました。馬刺しが一般的ですが、お肉屋さんに聞いたところ、他にもおいしい食べ方や使い道があるそうです。低カロリー・低コレステロールで、健康に良いと言われています。【どこで購入できるの?】市内の精肉店で販売しています。お土産として人気があり、通販を行う店舗もあります。
馬刺しだけではない、バラエティに富んだ美味しい馬肉料理【馬肉とは?】“桜肉”と呼ばれる馬の肉。南信州地域では古くから馬を様々な調理法で食べる習慣がありました。馬刺しが一般的ですが、お肉屋さんに聞いたところ、他にもおいしい食べ方や使い道があるそうです。低カロリー・低コレステロールで、健康に良いと言われています。【どこで購入できるの?】市内の精肉店で販売しています。お土産として人気があり、通販を行う店舗もあります。
飯田市伊豆木の鯖鮨は、江戸時代初期一帯を治めていた小笠原氏が戦の携行食を伊豆木八幡宮に奉納したのが始まりとされ、行事食・晴の食として発達しました。海のない信州の山村においては大変貴重である塩漬けのサバを運んだ伊那街道の愛知県岡崎から伊豆木へ至るルートは、地元では「鯖街道」と呼ばれています。現在も八幡宮の秋祭りの神様への供物で一本寿司と家庭における散らし寿司が作られており、伊豆木特有のすし文化です。長野県の伝統的な食文化を代表する「味の文化財」の一つ「飯田市伊豆木の鯖鮨」として、平成12年3月15日県選択無形文化財に指定されています。
飯田市伊豆木の鯖鮨は、江戸時代初期一帯を治めていた小笠原氏が戦の携行食を伊豆木八幡宮に奉納したのが始まりとされ、行事食・晴の食として発達しました。海のない信州の山村においては大変貴重である塩漬けのサバを運んだ伊那街道の愛知県岡崎から伊豆木へ至るルートは、地元では「鯖街道」と呼ばれています。現在も八幡宮の秋祭りの神様への供物で一本寿司と家庭における散らし寿司が作られており、伊豆木特有のすし文化です。長野県の伝統的な食文化を代表する「味の文化財」の一つ「飯田市伊豆木の鯖鮨」として、平成12年3月15日県選択無形文化財に指定されています。
五平餅(ごへいもち)とは、中部地方の山間部に伝わる郷土食です。ご飯を多少粒が残る程度につぶした(「半殺し」)ものをわらじ型、もしくは団子型に整形し、串に刺してタレをつけて焼いたものです。タレは味噌や醤油をベースにし、胡桃や胡麻、山椒の芽などを加えて作ります。五平餅の由来は、神道において神に捧げる「御幣」の形をしているからといわれています。「わらじ型」「眼鏡型」「御幣型」「棒状」のものなど、いろいろな種類の五平餅が食べられるのは南信州だけです。 【どこで食べられる?】伊那谷・木曽谷の郷土料理店、ドライブインなど。お土産としても人気があり、通販を行う店舗もあります。
五平餅(ごへいもち)とは、中部地方の山間部に伝わる郷土食です。ご飯を多少粒が残る程度につぶした(「半殺し」)ものをわらじ型、もしくは団子型に整形し、串に刺してタレをつけて焼いたものです。タレは味噌や醤油をベースにし、胡桃や胡麻、山椒の芽などを加えて作ります。五平餅の由来は、神道において神に捧げる「御幣」の形をしているからといわれています。「わらじ型」「眼鏡型」「御幣型」「棒状」のものなど、いろいろな種類の五平餅が食べられるのは南信州だけです。 【どこで食べられる?】伊那谷・木曽谷の郷土料理店、ドライブインなど。お土産としても人気があり、通販を行う店舗もあります。
おたぐりとは、馬のもつ(腸)の煮込み料理のことです。馬は腸が長く、20〜30メートルもあるそうです。下ごしらえは、腸の内容物を取り出して、塩水などできれいに洗いますが、その際に腸をたぐり寄せながら洗うことから「おたぐり」と呼ばれるようになったと言われています。古くから日本有数の馬の生産地として知られ、馬肉の食文化が培われてきた南信州。貴重なたんぱく源であった馬を余すところなく味わおうと、肉だけでなく、内臓も工夫して食べられてきました。おたぐりは、飯田市や伊那市など伊那谷のローカルフードです。南信州の居酒屋・定食屋・郷土料理店ほか、地元のスーパーでも販売されています。お土産としても人気があり、通販を行う店舗もあります。
おたぐりとは、馬のもつ(腸)の煮込み料理のことです。馬は腸が長く、20〜30メートルもあるそうです。下ごしらえは、腸の内容物を取り出して、塩水などできれいに洗いますが、その際に腸をたぐり寄せながら洗うことから「おたぐり」と呼ばれるようになったと言われています。古くから日本有数の馬の生産地として知られ、馬肉の食文化が培われてきた南信州。貴重なたんぱく源であった馬を余すところなく味わおうと、肉だけでなく、内臓も工夫して食べられてきました。おたぐりは、飯田市や伊那市など伊那谷のローカルフードです。南信州の居酒屋・定食屋・郷土料理店ほか、地元のスーパーでも販売されています。お土産としても人気があり、通販を行う店舗もあります。
山の恵みの中で、いまもっとも注目を浴びているのがジビエ(gibier)です。ジビエとは野生の狩猟肉をさすフランス語で、日本では一般的に「山肉」と呼ばれています。昔から、人間にとって大切なタンパク源でした。山肉は「臭い」「クセがある」という先入観は、いまや過去のものになりました。腕の確かな猟師と料理人の手にかかれば、ジビエの味わいはまさにクセになる美味しさです。ジビエ料理は、山に囲まれ、新鮮な山肉が手に入る南信州地域ならではの贅沢です。
山の恵みの中で、いまもっとも注目を浴びているのがジビエ(gibier)です。ジビエとは野生の狩猟肉をさすフランス語で、日本では一般的に「山肉」と呼ばれています。昔から、人間にとって大切なタンパク源でした。山肉は「臭い」「クセがある」という先入観は、いまや過去のものになりました。腕の確かな猟師と料理人の手にかかれば、ジビエの味わいはまさにクセになる美味しさです。ジビエ料理は、山に囲まれ、新鮮な山肉が手に入る南信州地域ならではの贅沢です。
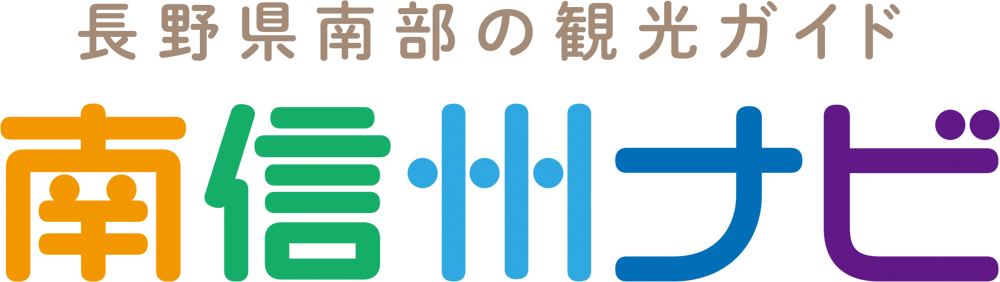
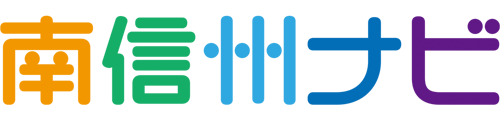











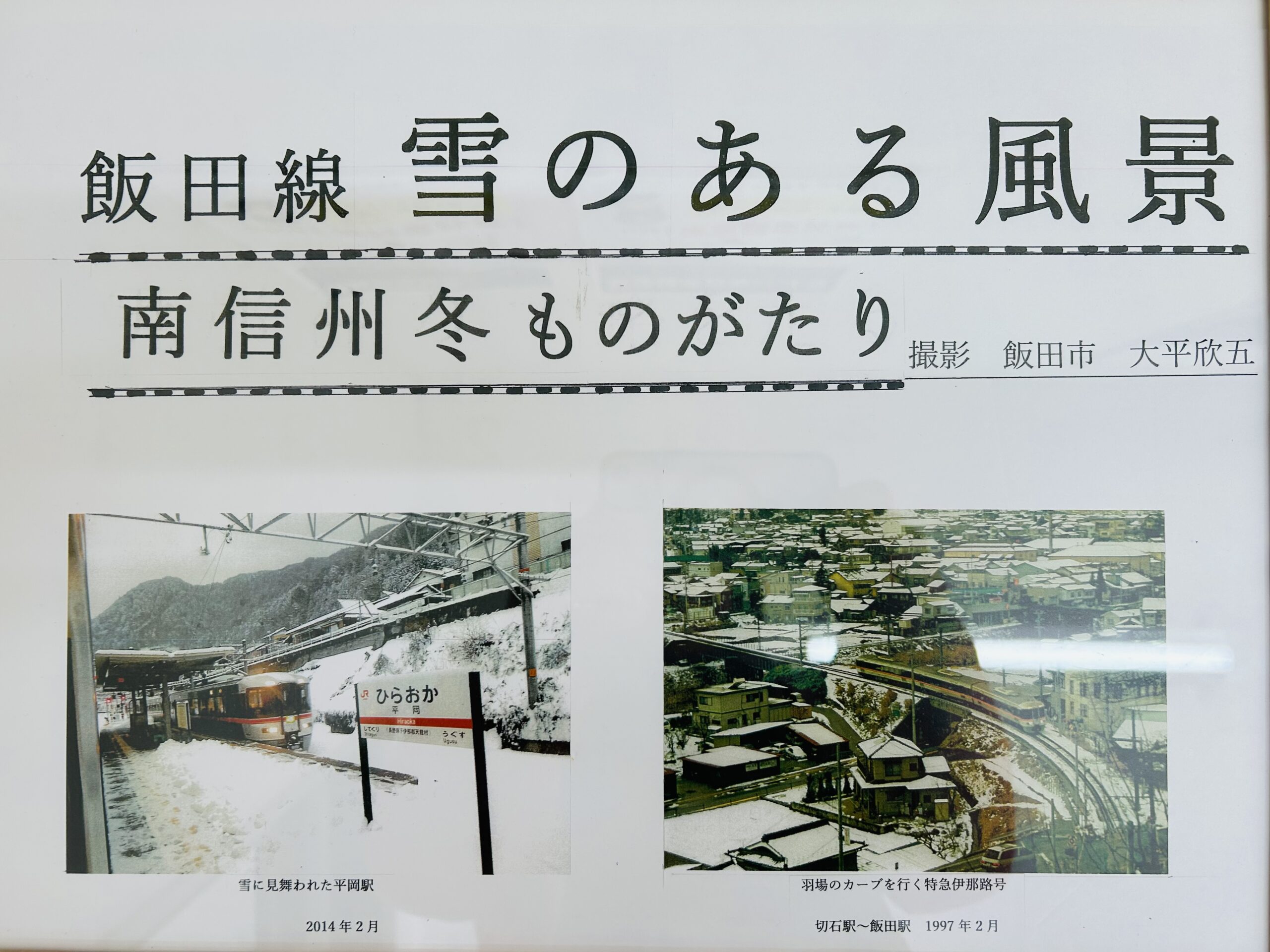

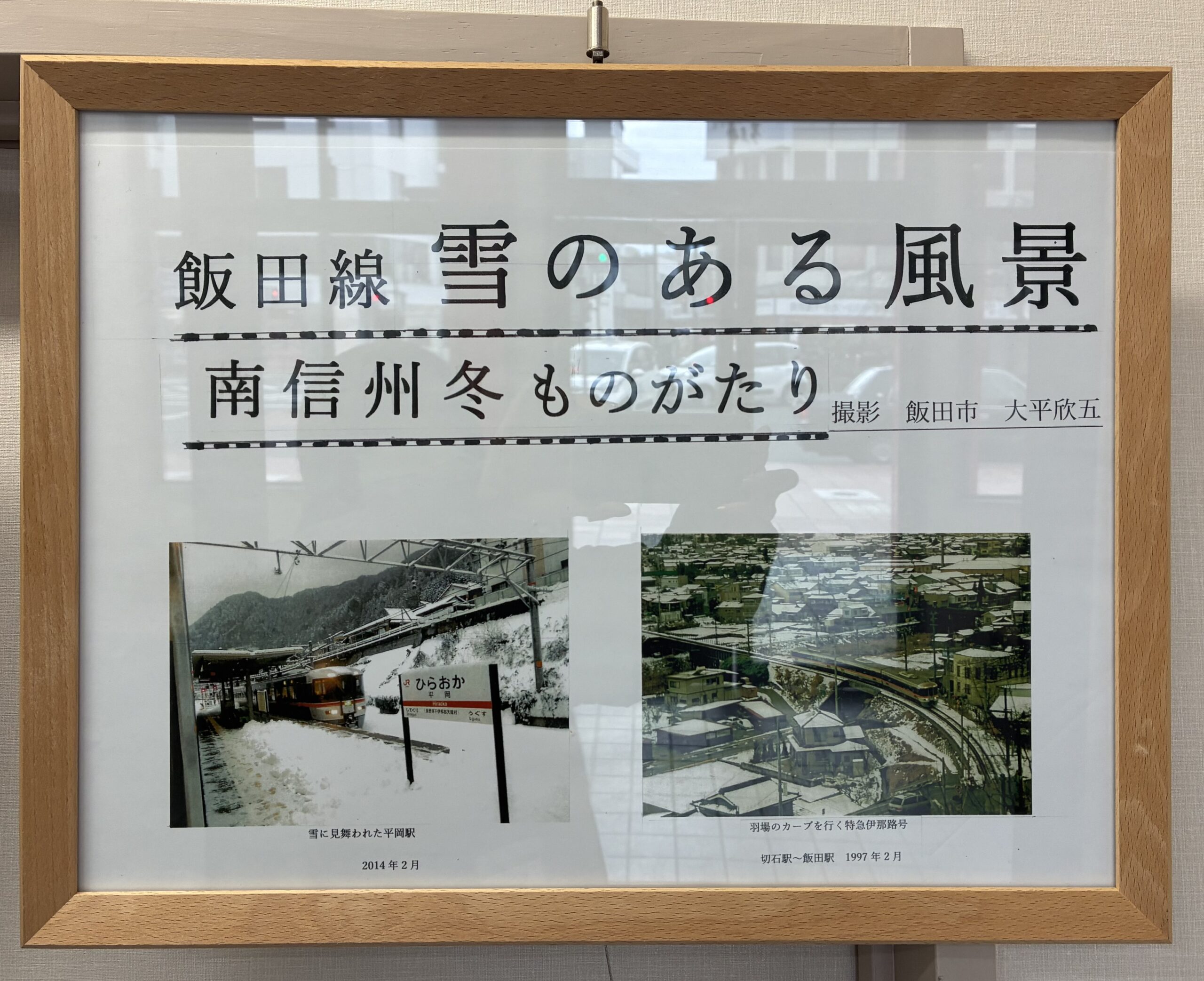

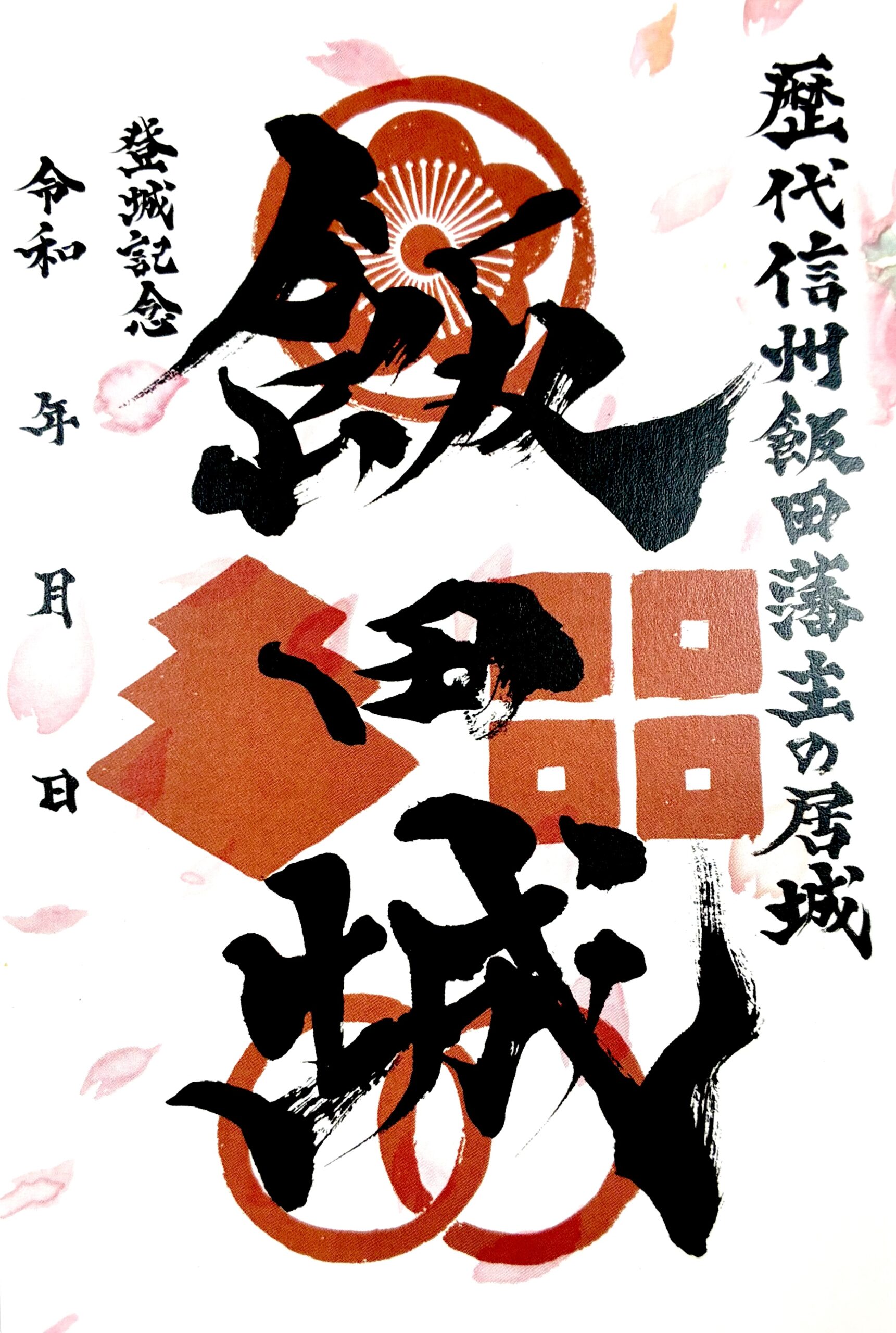


-scaled.jpg)